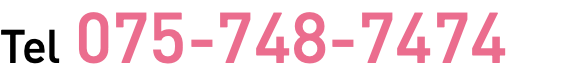こんにちは。京都市伏見区にある「ひらうち歯科」です。
歯周病は、歯を失う原因の一つとして広く知られていますが、その進行を止めたり、リスクを減らしたりできるのか疑問に思う方もいるでしょう。特に「歯周病は治るの?」という疑問は多くの方がお持ちになります。
この記事では、歯周病が治るのかという疑問に答え、進行を防ぐためにできることについても詳しく解説していきます。
目次
歯周病とは

歯周病は、歯を支える歯ぐきや歯槽骨(しそうこつ)などの歯周組織に炎症が発生する疾患で、炎症が進むと歯を失うリスクが高まります。成人の多くがかかっている病気ともいわれており、歯周病を放置すると歯を支える骨が破壊され、最終的には歯のぐらつきや脱落につながります。
初期段階であれば、適切な歯磨きと歯科医院での清掃で元の健康な歯肉に戻る可能性がありますが、進行すると治療をしても完治するのは難しく、症状の改善を目指すことになります。
歯周病の主な原因
歯周病の発症・進行には様々な原因が関係しています。直接的な原因は、プラークと呼ばれる細菌のかたまりです。プラークは歯と歯ぐきの境目に蓄積し、放置するとやがて歯石となって歯面に固着し、歯周病を悪化させます。
また、喫煙も歯周病のリスクを高める要因です。タバコに含まれる有害物質が歯ぐきの血行を悪化させ、免疫機能の低下を招きます。その結果、歯周病の進行を防ぐ力が弱まり、重症化しやすくなるのです。
また、糖尿病は歯周病と強く関連している疾患のひとつです。血糖値のコントロールが不十分な状態では、歯ぐきの炎症が治りにくくなり、歯周病が進行しやすくなります。歯周病があると血糖値のコントロールが難しくなるという相互作用も報告されています。
そのほかにも、ストレスや睡眠不足といった生活習慣の乱れも歯周病のリスクを高めます。免疫力が低下すると、歯ぐきの炎症が起きやすくなるためです。
歯周病の進行段階と症状
歯周病は、初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないため気付きにくく、進行するほど歯を支える組織が徐々に破壊されていきます。ここでは、歯周病の進行段階とそれぞれの症状について解説します。
歯肉炎
歯周病の初期段階が歯肉炎(しにくえん)です。プラークが歯と歯ぐきの間にたまると、その刺激によって歯ぐきが赤く腫れ、ブラッシング時に出血することがあります。
炎症は歯茎に留まっており、顎の骨(歯槽骨)には影響は及んでいない段階です。しっかりと歯磨きでプラークを除去できれば、炎症が改善することが多いでしょう。
軽度歯周炎
歯肉炎から進行すると、軽度の歯周炎(ししゅうえん)になります。さらに歯ぐきの炎症が進行し、歯周病ポケットが深くなります。顎の骨の破壊が始まり、歯ぐきから出血しやすくなります。
また、口臭が発生し始めたり歯ぐきが痩せ始めたりするのも、この段階に見られる症状です。
中等度歯周炎
中等度の歯周炎になると、歯周ポケットがさらに深くなり、歯を支える骨が半分近くまで破壊されます。歯茎の腫れや出血に加えて、口臭が強くなったり、歯がぐらつく感覚が出たりするようになります。
冷たいものがしみたり、歯茎が痩せて歯が長く見えたりすることもあります。
重度歯周炎
この段階になると、歯槽骨の大部分が破壊され、歯がぐらぐらと動いている状態になります。また、歯周ポケットの深さは6mm以上となり、専用の器具を使用した強力な清掃や外科的な治療が必要になるのが一般的です。
痛みや膿,出血などの症状が現れることも多いでしょう。最悪の場合、抜歯が必要になる可能性もあります。
歯周病は治る?

歯周病によって破壊された歯周組織が、自然に元の状態に回復することはありません。そのため、歯周病は完治することは難しいと言われています。基本的には、状態が悪化しないように対応していくことになります。
しかし、初期段階の歯周病であれば、正しいセルフケアと歯科医院でのケアを受けることで、元の歯周組織に近い状態まで改善できるかもしれません。「完治しないなら無駄だ」と治療をあきらめる必要はないのです。
歯周病の進行を抑えるために大切なこと

歯周病は、適切なケアを行えば進行を抑えられる病気です。一度進行すると元の状態に完全に戻すのは難しいため、早期からの対策が重要といえるでしょう。
歯科医院での定期的なチェックと併せて、日常生活の中でできる予防と管理を継続していくことで、歯周病の影響を最小限に抑え、自分の歯を守り続けられます。ここでは、歯周病の進行を抑えるために大切なことをご紹介していきます。
正しい歯磨きの仕方を身につける
歯周病の進行を防ぐには、毎日の歯磨きを正しく行うことが基本です。特に、歯周ポケットの奥にたまった汚れを取り除くことが重要です。
歯磨きの際は、歯と歯ぐきの境目に毛先を45度の角度であて、小刻みに動かしましょう。力を入れすぎると歯ぐきを傷つけるため、やさしい力で行ってください。
デンタルフロスや歯間ブラシを併用する
歯ブラシだけでは、歯と歯の間に付着したプラークを完全に取り除くことはできません。そこで活躍するのが、デンタルフロスや歯間ブラシです。歯間部には歯周病菌が多く集まりやすく、取り除くことが難しいため、これらの補助清掃用具を使用することが重要です。
毎日のケアにフロスや歯間ブラシをプラスすることで、歯周ポケット内の細菌を除去しやすくなります。
定期的に歯科医院でクリーニングを受ける
毎日丁寧に歯磨きをしていても、セルフケアだけで歯垢を完全に除去することは難しいです。除去できたとしても、磨き残しが生じる可能性が高いでしょう。特に、歯周ポケットが深くなると歯ブラシの毛先が届かなくなり、歯垢や歯石がたまりやすくなります。
歯垢や歯石をそのままにすると歯周病菌が繁殖し、炎症が悪化しやすくなります。歯科医院で専門的なクリーニングを受けることで、自分では落としきれない汚れを除去し、歯周病の進行を抑えられるようになるでしょう。
歯科医院で行うクリーニングは、PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)と呼ばれます。歯科医師や歯科衛生士が、専門の器具や研磨剤を使って磨き残しや歯石を徹底的に除去します。
2〜3ヶ月ごとにプロによるケアを受ければ、セルフケアでは落とせない細菌を除去できるので歯周病の進行を食い止めることができます。
喫煙習慣を見直す
喫煙は、歯周病の大きなリスク要因の一つです。ニコチンやタールが血管を収縮させ、歯ぐきへの血流が悪くなることで免疫力が低下し、炎症が慢性化しやすくなるのです。
また、喫煙者は歯ぐきの出血が起こりにくくなるため、歯周病になっていても発見が遅れる傾向があります。治療の効果も出にくくなるので、歯周病治療の効果を最大限に引き出すためにも、禁煙や間欠的禁煙に取り組みましょう。
ストレス管理と生活リズムの改善
ストレスや生活リズムの乱れも、歯周病の進行に関係しています。強いストレスを抱えていると、体の免疫力が低下し、細菌に対する抵抗力が落ちることで歯周病が悪化することがあります。
また、睡眠不足は身体の回復を妨げ、炎症の治癒を遅らせる要因となります。規則正しい生活と十分な睡眠、適度な休息を心がけることは、歯周病対策としても非常に重要です。
食生活の見直し
食生活も、歯周病の進行に大きく関わっています。糖分の多い食事は細菌の餌になるため、甘いお菓子やジュースなどは控えるようにしましょう。
また、栄養バランスの取れた食事を心がけることも重要です。特に、ビタミンCやビタミンD、カルシウムなどは歯ぐきの健康を保つうえで欠かせません。
全身疾患の管理と薬の影響を把握する
糖尿病と歯周病は相互に悪影響を及ぼすことが知られており、血糖値が高ければ歯周病が悪化し、歯周病が進むと血糖コントロールが困難になるなど悪循環に陥ります。糖尿病のある方は、歯周病予防に特に注意が必要といえるでしょう。
また、骨粗鬆症の方や、服用している薬剤が骨密度に影響するもの(骨吸収抑制薬・抗リウマチ薬など)などの場合も注意が必要です。歯科医師に全身の健康状態を伝え、適切なタイミングで歯科治療を行うことが求められます。
まとめ

歯周病は完治が難しい病気ですが、日々のセルフケアと定期的な歯科医院でのメンテナンスを行うことで、悪化を防げます。歯周病を防ぐために大切なのは、毎日丁寧な歯磨き・歯科医院でのクリーニング・生活習慣の見直しを行うことです。歯周病が悪化すると歯を失うリスクが高まりますので、後悔する前に今日から対策を始めてみてはいかがでしょうか。
歯周病治療を検討されている方は、京都市伏見区にある「ひらうち歯科」にお気軽にご相談ください。
当院では、一般歯科だけでなく小児歯科や矯正歯科、審美歯科の診療も行っています。診療案内はこちら、ネット予約も24時間受け付けておりますので、ぜひご活用ください。








 ひらうち歯科
ひらうち歯科